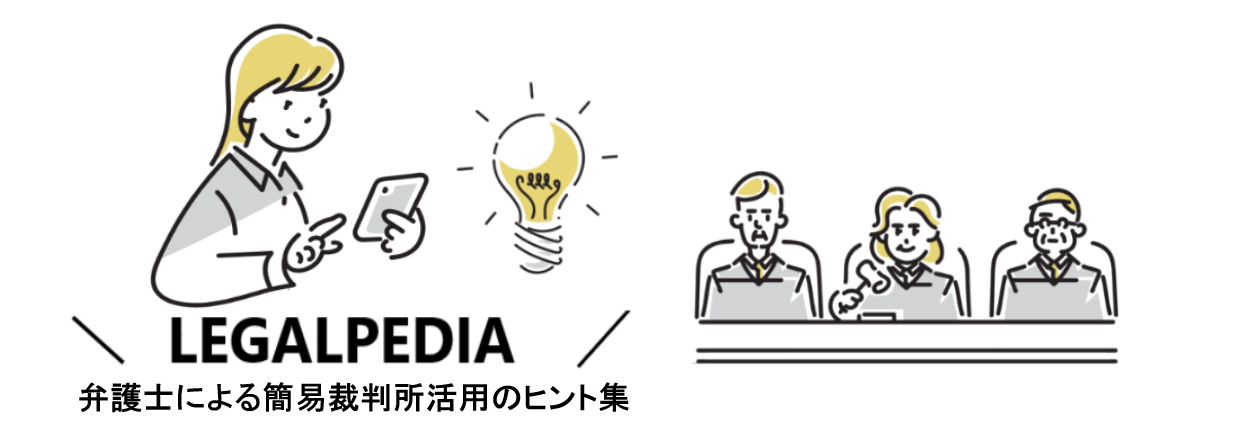事案の概要
高知県の南国市で、同市十市にある公設民営の保育園などの土地について、定期の借地契約が2022年末で終わり、新しい契約を結べるよう、高知簡易裁判所に民事調停を申し立てるとの報道がありました(公設民営の保育園が不法占拠状態に 借地契約結べず「申し訳ない」 朝日新聞デジタル 2023年3月18日)。
土地の貸主は神社で、市とは2003年から22年までを賃貸借期間とする事業用借地権設定契約を締結していました。
契約の終了が近づいてきた21年10月以降は、市と神社は新たな契約に向けて契約内容の交渉を行っていました。
しかし、借りている土地の上にある保育園が津波浸水想定区域にあり、市が保育園の移転を検討していることもあって、中途解約に関する内容で折り合いがつかず合意できなかったということです。
事業用借地権設定契約とは
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として、公正証書によって契約する定期借地権を、事業用定期借地権(借地借家法23条)といいます。
市と神社の間で結ばれていた期間を20年とする事業用借地権設定契約とは、借地借家法23条2項に基づく事業用定期借地権です。
借地借家法23条2項に基づく事業用定期借地権は、定期ではない通常の借地契約とは違い、借地契約の更新、建物が滅失・再築した場合の借地期間の延長、借地権の存続期間が満了した場合の建物買取請求権に関する規定の適用はありません。
賃貸借期間の満了後は、一般的には、借主が借りていた土地上の建物を撤去し、更地にして貸主に返還します。
事業用定期借地権は、期間の満了によって終了するため、満了後は不法占拠の状態となります。
満了後も引き続き借りたい場合には、再度契約をすることとなります。
事業用定期借地契約における中途解約と違約金
中途解約は権利の留保が必要
事業用定期借地契約は、一定の確定的な存続期間が定められる期間の定めのある契約で、期間内には賃貸人、賃借人のいずれからも、原則として一方的な意思表示による解約はできません。
民法は618条で、期間の定めのある賃貸借契約についての中途解約権が留保されている場合の解約申し入れを規定しますが、解約権の留保がされていない場合は解約できないのです。
そのため、事業用定期借地契約を締結する場合、借地人側が中途解約できる余地を残しておきたい場合は、あらかじめ解約内容に中途解約権を留保する旨の特約を入れておく必要があります。
高額な違約金もただちに無効とはならない
中途解約権を留保する旨の特約を入れるとしても、解約の際に発生する違約金の定めをどうするかという点も問題となります。
事業用定期借地契約で土地を貸す賃貸人は、長期間の土地の安定的な有効活用を目的としており、通常、複数の賃借希望者から問題なく契約期間満了まで借り続けてくれそうな契約相手を選択します。
せっかく契約した賃借人から中途解約され、新しい賃借人が見つからなかったり、新しい賃借人との契約はできそうだが賃料を大幅に下げる必要があるとなると、長期間の土地の有効活用という目的を達することができず、契約で定めた存続期間満了までの賃料収入を失うという損失を負うこととなります。
賃貸人の期待を保護するという考え方から、中途解約は認めるとしても残存期間の賃料全額が違約金であると定められることもあります。
たとえば、20年の契約をした場合、12年間で解約をする場合、契約自体は終了させることができるが残りの8年分の賃料相当額は違約金として支払うということです。
一見すると、あまりに賃借人に不利ではないかと思えるかもしれませんが、事業用定期借地権では借主も事業者であり、存続期間は双方の協議により決定されること、中途解約は契約時に経営判断の見通しを誤った賃借人の問題でもあるといえます。
そのため、残存期間の賃料全額を違約金とする定め自体がただちに不合理で無効だとはなりません。
とはいえ、実際に賃借人が撤退し、違約金の額が裁判で争いとなるような場合は、賃借人撤退後に賃貸人が新たな賃借人と借地契約を結べたか等の事情も考慮の上、違約金の範囲が一定期間にとどめられることが予想されます1。
着地点を見出すための民事調停
本件では、保育園の将来的な移転を市が検討していることもあって、期間満了後に再度の契約をするにあたり、市が、中途解約権の留保や、中途解約の際に違約金があまり高額とならない条件での契約内容を求めたようです。
賃借人側としては、その条件であれば市とは期間満了後の再契約はせず、中途解約権の留保を希望しなかったり、中途解約権を留保するとしても違約金をしっかり支払うと取り決めをしてくれる新しい賃借人を探す方が経済合理的な選択となります。
再度の契約といっても、実質は新規の契約なので、賃料や諸条件については、従来のものが引き継がれるわけではなく、賃貸人側が再契約をしないといけない義務はありません。
賃借人から再契約を求めるための法的な根拠はないので、訴訟をしても賃借人側には勝ち目はありません。
法的根拠はないが、第三者を入れて条件面をもう少しなんとか話し合いできないかという場合の手段として、民事調停が使われています。
本件では、なにより、現在も保育園が運営中であることに加え、再契約自体が全く考えられないわけではなく、報道によると、折り合いがついていないのは中途解約に関してだけのようです。
ポイントは絞られているので、第三者を入れることで、実情に沿った着地点に落ち着くことが期待されます。